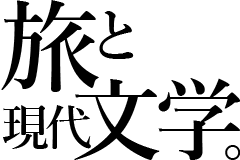いとうせいこう『ワールズ・エンド・ガーデン』レビュー
書誌情報
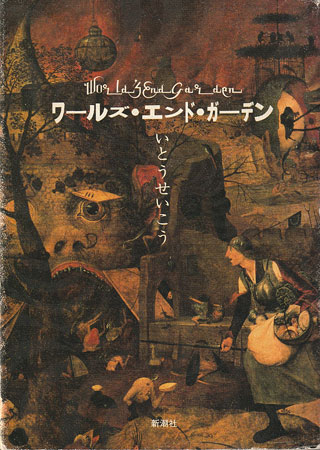
レビュー
長めの感想
絶版ものなんですがすすめてみたいんですよね。古本屋でも探してみてくださいな。
東京の一角に、最先端の流行を創っているクリエイター達が住み、アラビア語の看板が連なり、スキンヘッドにターバンを巻いた少年達がスケボーを駆り、ドラッグが横行する(という著者が当時思い描いた)カッコイイ街があるわけです。その街に記憶喪失の老人が入り込んでくることから物語が動き出します。
浮浪者然とした老人なんだけれど、「予言能力がある」ということで信奉者が彼の周りに集まり、宗教の原初形態のようになってゆくわけですね。老人を中心に急速に結束を強めてゆく集団と、彼らを街から排除しようとする勢力との対立が主軸となる作品です。
このあたり、明確に「オウム的」ですよね。ちなみにあの一連の事件の四年前に書かれた作品で、「オウムを予言した小説」と言われたりもします。
いとうらしさ全開なイスラムポップな流行描写に、新興宗教のドロドロした蠕動がのしかかり、さらに「アイデンティティ」の物語が積み込まれます。
「いわゆるアイデンティティ探しの小説に読まれるんだけど、そうじゃないんだよね」って著者は雑誌インタビューで言ってたんだけれど、これはやっぱりアイデンティティ探しでしょ。
主人公は老人側、街側、どちらともつかない曖昧な位置にいるんです。いや、街の運営委員の一人であるから街側につくべきなんですが、老人のパワーにも取り込まれてゆくんです。つまり老人とのつながりによって自分が存在している、変幻自在な老人によってこそ、自分が規定される、という風に。
老人は記憶喪失というか完全に病理の中にいるんですが、彼自身が巨大な混沌装置として、主人公はじめ皆を飲み込んで狂わせてゆくわけです。主人公が老人に向かって発した「お前は誰だ」という言葉がハウリングするように増幅してしまうあたり、ゾクゾクします。
恐らく著者はオーソドックスがやりたかったんだと思うんです。主題も文体も、実に正統的です。文学の力というものを試した作品といえるでしょうね。メビウスのウロボロスみたいに永遠に回り続ける回路となって、怒濤のごとく流れる終盤は文学の喜びそのものですよ、もう。
あと、いろいろと魅力的な登場人物は多いんですが、アウトサイドにいながら物語を読み解く役割も負っている洗脳外しの「解体屋」が特にカッコイイです。同意される方は『解体屋外伝』という作品があるので読みましょう。